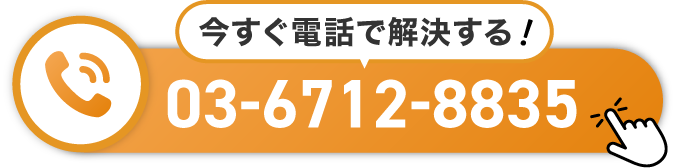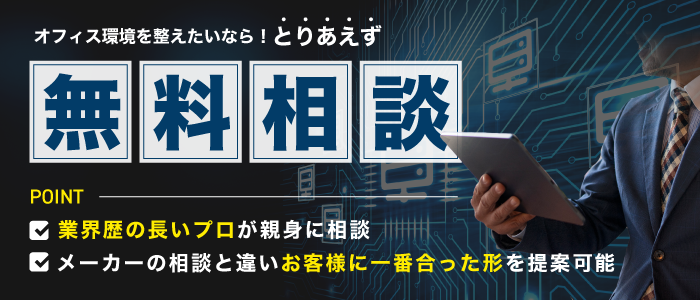中小企業のセキュリティ|助成金はどれくらいもらえる?対策の必要性も
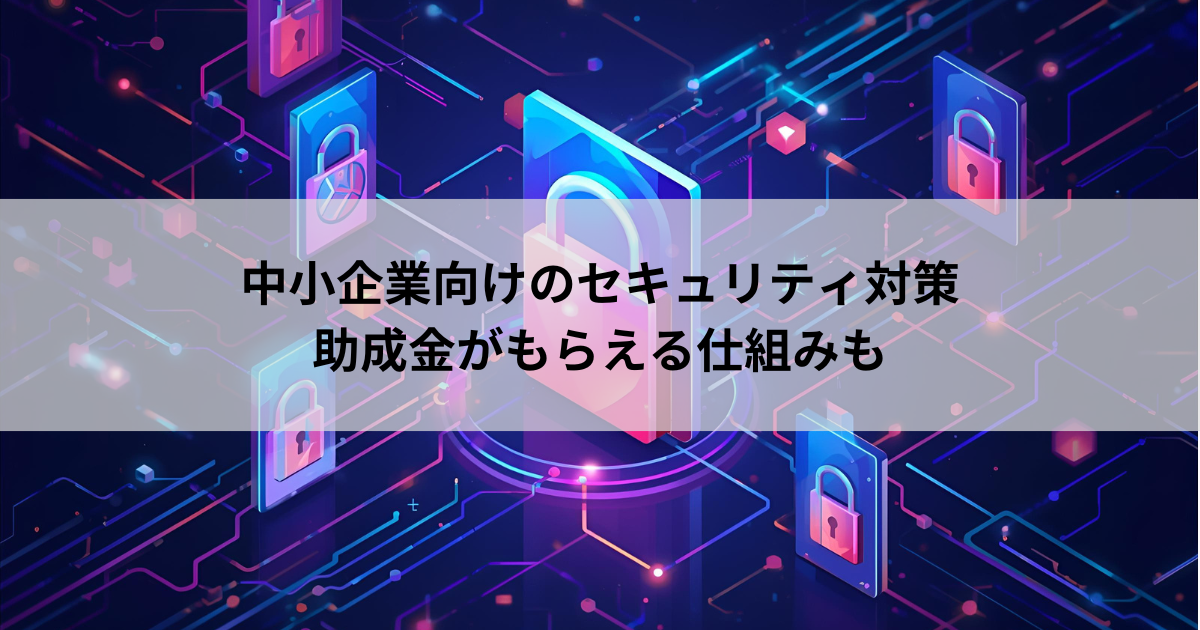
サイバー攻撃の標的は今や中小企業にも広がっています。
限られた予算でも、助成金を活用すれば確実なセキュリティ対策が可能です。
この記事では、UTMの必要性や社内ルール整備のポイントをわかりやすく解説します。
- 中小企業のセキュリティ対策について知りたい人
- セキュリティ対策をして助成金をもらいたい人
- 中小企業におすすめのセキュリティ対策の内容を知りたい人

中小企業がセキュリティ対策を行う必要性
たとえ小規模な企業であっても、「自社は狙われない」という考え方はすでに通用しません。
早期のセキュリティ対策こそが、会社の信頼と事業継続を守る最善の手段といえます。
ここでは、どうして中小企業にセキュリティ対策が必要なのかを解説します。
攻撃対象が中小企業に広がっているため
サイバー攻撃というと大企業を狙ったものと思われがちですが、実際には中小企業が被害を受けるケースが年々増えています。
理由のひとつは「セキュリティが手薄になりやすい」ことが挙げられます。
大企業と取引を行う中小企業は、サプライチェーンの一部として標的にされることも多く、攻撃者にとって狙いやすい入口となってしまうのです。
実際、情報処理推進機構(IPA)の調査でも、中小企業の約6割が何らかのセキュリティインシデントを経験しているとされています。
サイバー攻撃の内容が巧妙化しているため
近年の攻撃は、ウイルスメールや不正アクセスといった単純な手口だけではありません。
業務メールを装った「なりすまし」や「請求書偽装」、パソコンを人質に取るランサムウェア攻撃など、手法はますます巧妙化しています。
攻撃の目的も、金銭だけでなく、取引先情報や技術データの奪取など多岐にわたります。
ひとたび感染・侵入を許すと、業務停止や顧客流出など、経営に直結する深刻な被害につながるおそれがあります。
情報資産を守るため
中小企業にとっても、顧客情報や営業データ、設計図面などは大切な経営資産です。
これらが流出・改ざんされると、取引先からの信頼を失い、契約停止や損害賠償に発展することもあります。
とくにクラウドサービスやリモートワークの普及により、社外からのアクセスが増え、情報漏えいリスクが高まっています。
ハードウェアやネットワークだけでなく、社員一人ひとりの情報管理意識を高めることも欠かせません。
法令・ガイドラインに対応するため
個人情報保護法の改正や、IPAが公表する「中小企業の情報セキュリティガイドライン」など、企業として取り組むべき基準や指針も年々整備されています。
取引先や行政とのやり取りの中で、セキュリティ体制の整備状況を確認される場面も増えています。
法令やガイドラインに沿った管理体制を整えておくことは、コンプライアンス遵守と企業信用の維持のために不可欠です。
中小企業向けセキュリティ対策一覧
基本的な対策を組み合わせることで、限られたコストでも堅実なセキュリティ体制を構築できます。
UTM(統合脅威管理) の導入
UTM(Unified Threat Management)は、1台で複数のセキュリティ機能をまとめて管理できる装置です。
ファイアウォールや不正侵入防止(IPS)、ウイルス検知、スパムメール対策、Webフィルタリングなど、通常は個別に導入する必要がある機能を統合しています。
中小企業では、セキュリティ専門の担当者を置けないケースも多いため、UTMを導入することで運用負荷を抑えながら、外部からの攻撃をまとめて防御することができます。
最近ではクラウド型UTMも普及しており、初期費用を抑えて利用できるプランも増えています。
PC・サーバのウイルス対策ソフト導入
社員のパソコンや社内サーバには、最新のウイルス対策ソフトを必ず導入しておきましょう。
ランサムウェアやトロイの木馬などのマルウェアは、メールやWebサイト経由で簡単に侵入してきます。
ウイルス対策ソフトは、未知の脅威にも対応できる「AI検知型」や「ふるまい検知型」を選ぶとより安心です。
さらに、管理者が全端末の状態を一括で確認できる「集中管理型ソフト」を選べば、社員のセキュリティ意識に依存せず、組織としての対策レベルを維持できます。
OSやソフトウェアの定期アップデート
セキュリティの穴(脆弱性)は、古いOSや未更新のアプリケーションから生まれることが多いです。
攻撃者はそうした脆弱性を狙い、自動で侵入を試みるプログラムを使うため、更新を怠ると簡単に攻撃を受けてしまいます。
WindowsやmacOSなどのOS、Officeソフト、Webブラウザなどは、更新通知が出たら早めにアップデートすることが鉄則です。
もし端末が多く管理が大変な場合は、自動更新機能やパッチ管理ツールの利用を検討しましょう。
メールの添付・URL検知機能の利用
中小企業へのサイバー攻撃の多くは、メールをきっかけに発生しています。
添付ファイルを開いたり、本文のリンクをクリックしたことでウイルス感染するケースが後を絶ちません。
こうしたリスクを減らすには、メールサーバやゲートウェイに添付ファイルやURLの自動検知機能を導入するのが効果的です。
受信前に不審メールをブロックできるため、社員が誤って開いてしまう事故を防げます。
また、月に一度でも「不審メールの見分け方」などの啓発を行うと、人的ミスを防ぐ意識づけにもつながります。
中小企業のセキュリティポリシー・社内規定とは
中小企業がサイバー攻撃から自社を守るためには、機器やソフトを導入するだけでなく、社内全体で「ルール」を定めることも欠かせません。
その中心となるのが「セキュリティポリシー」と「社内規定」です。
セキュリティポリシーと社内規定の違い
セキュリティポリシーとは、企業として情報セキュリティをどのように考え、どのように守るかを示した基本方針のことです。
たとえば「お客様情報を外部に漏らさない」「社内ネットワークを安全に運用する」といった、組織の理念や方針レベルの内容が中心になります。
一方で社内規定は、そのポリシーを実際の業務でどう実践するかを具体的に示したルールです。
たとえば「パスワードは8文字以上」「外出時はPCをロック」「退職時にアカウント削除」など、社員一人ひとりが守るべき行動を明文化します。
この2つをきちんと分けて整備することで、組織全体で統一感のあるセキュリティ対策が可能になります。
無料で使えるテンプレート(pdf埋め込みやりたい、IPAのファイル)
セキュリティポリシーをゼロから作るのは大変ですが、IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)が中小企業向けに無料テンプレートを公開しています。
このテンプレートでは、会社名を入力していくだけで基本方針・対策方針・運用ルールを簡単に作成できます。
社内規定のテンプレート(wordファイルで開きます)|独立行政法人情報処理推進機構
中小企業が活用できるセキュリティ関連助成金
補助金をうまく活用すれば、初期費用を抑えながら安心・安全なオフィス環境を整えることができます。
セキュリティ機器の導入を検討する際は、助成金の対象となるかも必ずチェックしておくとよいでしょう。
IT導入補助金
中小企業・小規模事業者がITツールを導入する際に利用できる補助金で、セキュリティソフトやUTM(統合脅威管理)機器の導入も対象になります。
導入費用の最大3分の2(上限450万円)が補助されるケースもあり、クラウド型セキュリティやリモートワーク環境整備などにも活用可能です。
IT導入支援事業者に登録されている企業を通じて申請する必要があるため、まずは導入を検討している販売店やITベンダーに相談してみましょう。
サイバーセキュリティお助け隊サービス補助金
IPA(情報処理推進機構)が中心となって実施している制度で、専門事業者によるサイバーセキュリティ監視・相談サービスの利用料を補助してくれるものです。
中小企業が自力で高度なセキュリティ体制を整えるのは難しいため、外部の専門家支援を低コストで受けられる点が特徴です。
UTM導入や監視サービスと併用すれば、より強固な対策が可能になります。
地方自治体の独自補助
自治体によっては、情報セキュリティ対策費用を補助する独自制度を設けている場合もあります。
たとえば東京都や大阪府などでは、中小企業向けにUTMやセキュリティ診断費用を助成する制度が実施されています。
地域によって条件や上限額が異なるため、最新情報は各自治体のホームページで確認しましょう。
セキュリティ対策のご相談はITDまで!

中小企業にとって、セキュリティ対策は「やるべきこと」から「経営を守る必須事項」へと変わりつつあります。
しかし、どんな機器を導入すべきか、どの範囲まで整備すれば十分なのかを判断するのは簡単ではありません。
ITDでは、UTM(統合脅威管理)をはじめとするオフィス向けセキュリティソリューションを、企業の規模や課題に合わせてご提案しています。
初期費用を抑えたい場合は、リース導入のサポートも可能です。
「セキュリティ対策を始めたいけれど、何から手をつければいいか分からない」
そんな中小企業のご担当者さまは、まずはお気軽にご相談ください。
↓👇オフィス環境の安全を、コストを抑えて確実に整えるお手伝いをいたします!👇↓
※お問い合わせの際は、「無料相談バナーを見た」とお伝えください。