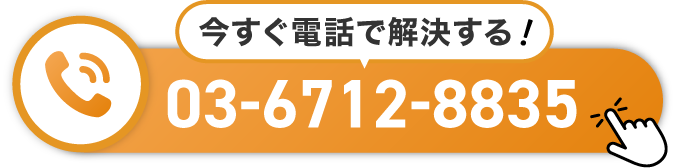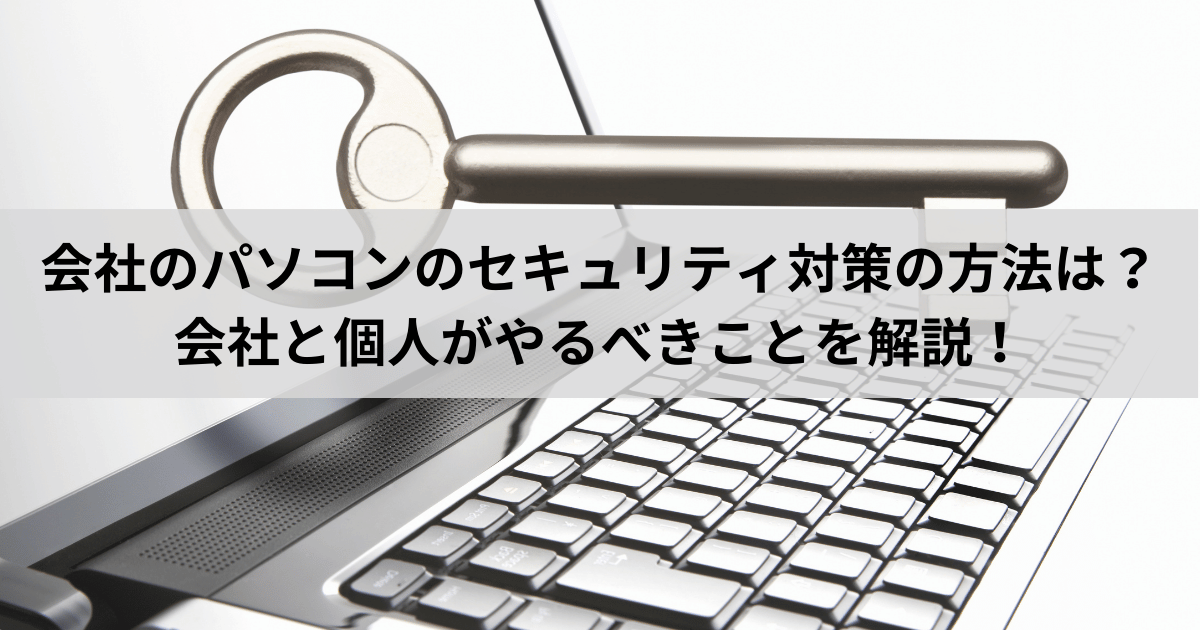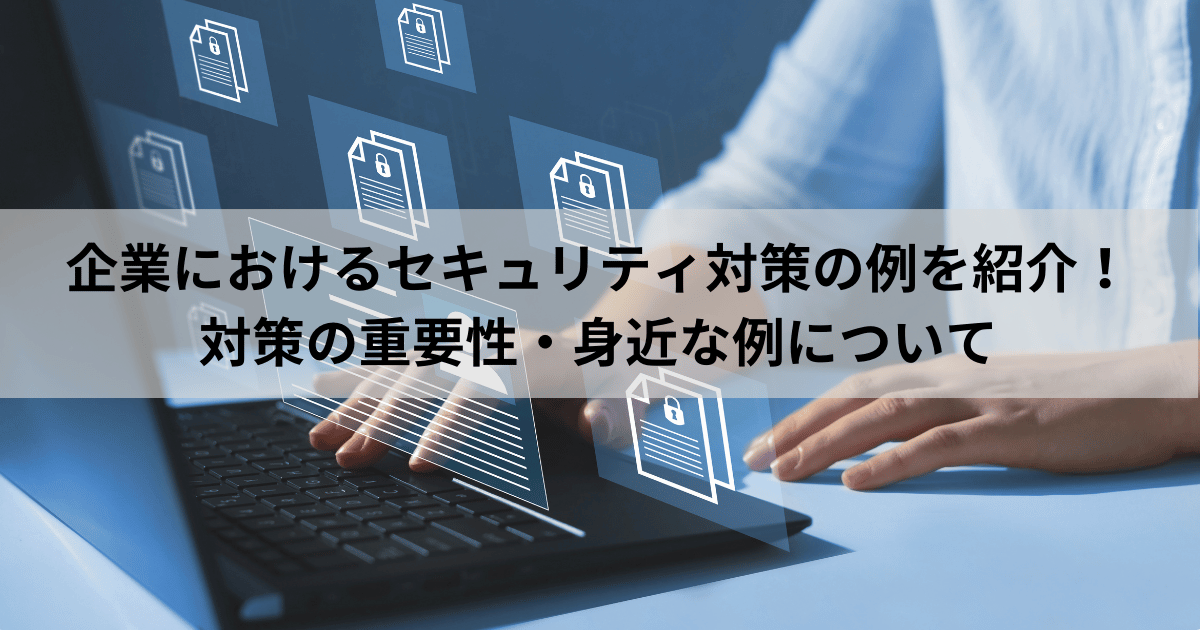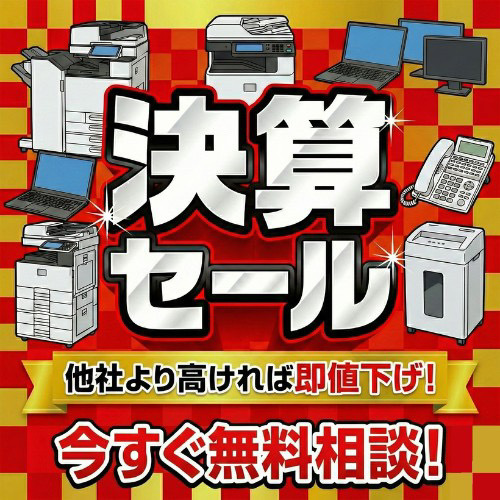個人情報の漏洩を防ぐための対策とは?事例から学ぶ企業と個人の守り方
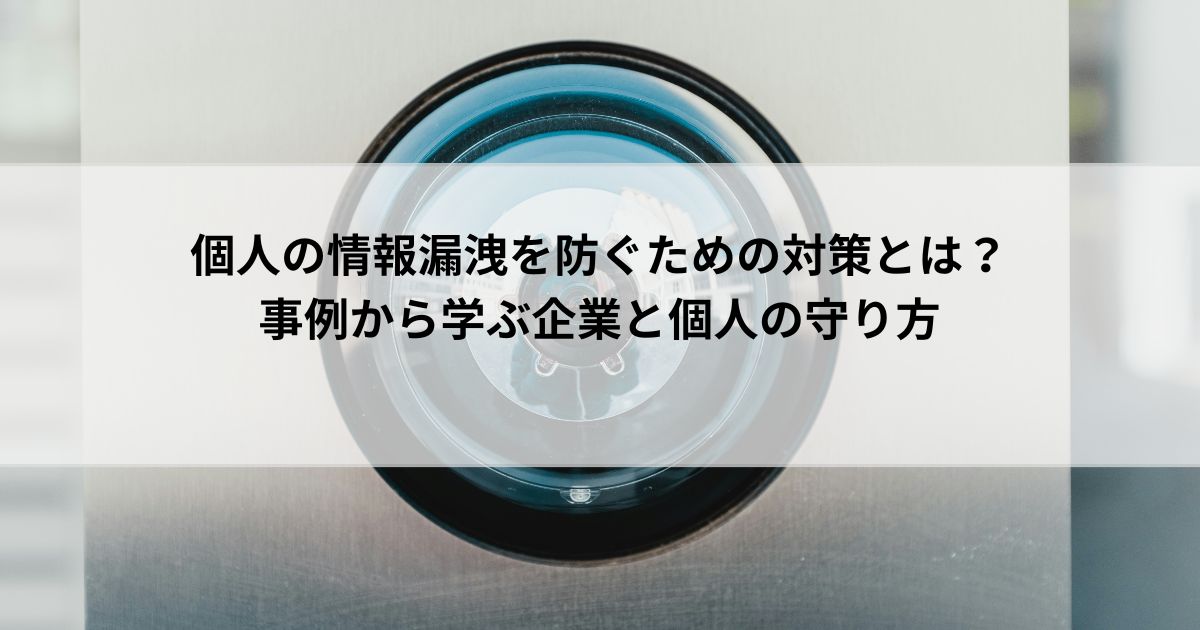
スマホやSNSが日常化した今、個人情報の管理は誰にとっても他人事ではありません。
企業の情報漏洩ニュースも連日のように報じられています。
本記事では、個人が注意すべき情報漏洩の仕組みや実際の事例、そして防止策を徹底解説します。
- スマホやパソコンで個人情報を扱う機会が多い方
- 自社の情報管理体制に不安がある経営者・総務担当者
- 法人向けセキュリティ対策を検討している方
個人の情報漏洩とは?

情報漏洩とは、他者に知られてはならない個人や企業の情報が、意図せず第三者に渡ってしまうことを指します。
悪意のある攻撃だけでなく、うっかりミスによっても発生するため、注意が必要です。
個人情報の定義
個人情報とは、特定の個人を識別できる情報のことを指します。
たとえば、氏名・住所・電話番号・メールアドレス・マイナンバー・顔写真などが該当します。
また、近年では位置情報や閲覧履歴も「個人関連情報」として重視されています。
以下のような情報は「個人情報」に該当します。
- 氏名・住所・生年月日
- 電話番号・メールアドレス
- マイナンバー・健康保険証番号
- 顔写真・音声データ
- 位置情報や購買履歴などの行動履歴
企業・個人情報の漏洩リスクとは
情報漏洩のリスクは多岐にわたります。
企業においては顧客情報や従業員データが漏洩すれば、信用失墜や損害賠償に直結します。
一方、個人レベルでは、なりすまし被害や詐欺に巻き込まれるリスクが高まります。
スマホ利用と情報流出の関係
スマホは便利な反面、情報流出の入口になりがちです。
アプリからの不正アクセス、公衆Wi-Fiの利用、SNSへの不用意な投稿などがきっかけで、個人情報が外部に漏れるケースは後を絶ちません。
スマホで起こりうる情報漏洩リスクの例
| リスク要因 | 具体的な例 | 対策のヒント |
|---|---|---|
| 公衆Wi-Fi | 通信の盗聴 | VPNの利用や接続回避 |
| アプリの権限過剰 | カメラや連絡先へのアクセス | アプリ権限を見直す |
| SNSの不用意な投稿 | 写真に住所・学校名が映り込む | 投稿前の確認を習慣化 |
| OSの未更新 | セキュリティ脆弱性が残る | 常に最新バージョンに更新 |
個人の情報漏洩の事例3選

実際に発生した情報漏洩の事例から、個人や企業がどのようなリスクにさらされているかを学びましょう。
トヨタ自動車株式会社
2023年5月、トヨタ自動車は顧客215万人分の車両情報が漏えいした可能性があると公表しました。
漏えいした恐れのある情報には、ドライブレコーダー映像、車載端末ID、位置情報などが含まれます。
原因はクラウド環境の設定ミスによるもので、人為的なミスとされています。
出典:TOYOTA
株式会社SODA
2023年6月、スニーカー通販サイト「SNKRDUNK」で不正アクセスが発覚し、約275万件の会員情報が漏えいした可能性が明らかになりました。
漏えいした恐れのある情報には、氏名や連絡先、購入履歴などが含まれます。
原因は不正なリクエストに対し、データベースの情報を含んだ応答が返されたことによるものでした。
出典:SNKRDUNK
JR東日本
2020年3月、JR東日本は「えきねっと」アプリへの不正アクセスにより、3,729件のアカウントが不正ログインされた可能性を発表しました。
そのうち13件では個人情報の閲覧が確認され、氏名や連絡先、クレジットカード情報の一部などが対象となりました。
原因は海外からの異常なログイン試行とされています。
出典:日経XTECH
個人でできる情報漏洩の対策
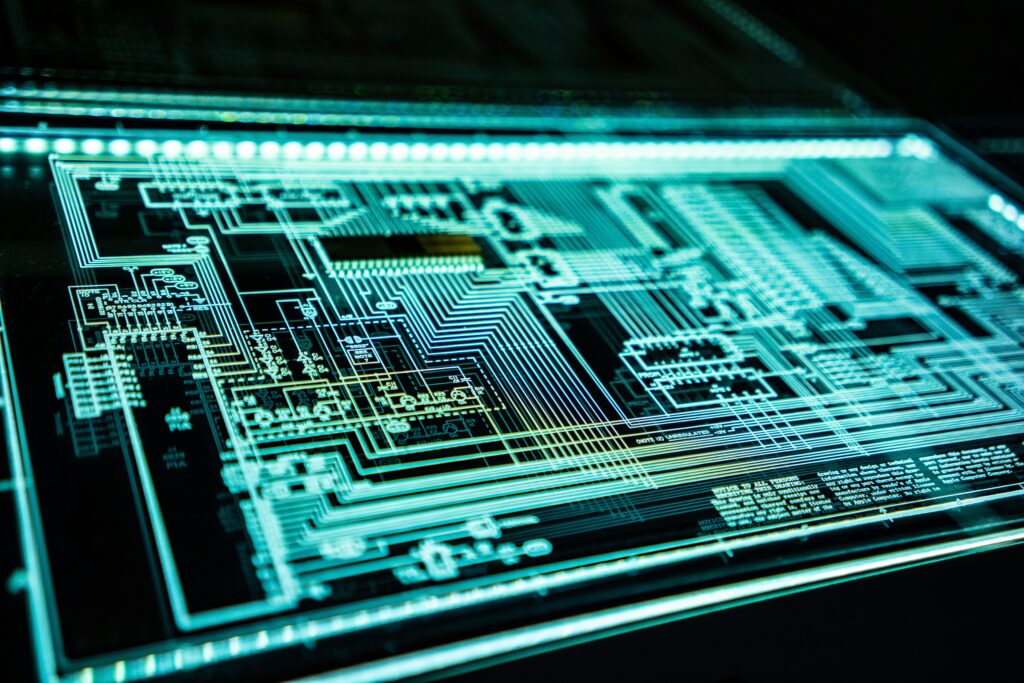
自分の情報を守るために、今すぐ実践できる具体的な対策を紹介します。
危険なサイトとWi-Fiを避ける
不審なURLや公式でないアプリサイトにアクセスすると、個人情報が盗まれる恐れがあります。
さらに、パスワード保護がないフリーWi-Fiでは通信内容が傍受されやすく、非常に危険です。
通信は信頼できるネットワークを使い、サイトのURLに「https」が含まれているかを必ず確認しましょう。
- サイトURLに「https」がある
- 公共Wi-FiではVPNを使用
- 不審なリンクを開かない
- アプリは公式ストアからのみDL
紙・デジタル情報を正しく捨てる
不要な書類やデジタルデータの処分も情報漏洩の盲点です。
紙は裁断処理を行い、USBやパソコン内のファイルは専用の消去ソフトで完全削除しましょう。
ゴミ箱に入れただけでは復元可能な場合があるため、確実な方法での処理が必要です。
▼正しい情報の廃棄方法チェックリスト
- 書類はシュレッダーで裁断する
- 領収書・送り状など個人情報を含む紙類も処理する
- USBやHDDのデータは専用ツールで完全削除する
- ゴミ箱に入れただけでは削除されないことを理解する
セキュリティソフトを更新する
セキュリティソフトは、古いままだと最新のウイルスやマルウェアに対応できません。
常に最新バージョンに保つことで、未知の攻撃への耐性を強化できます。
自動更新機能を活用し、OSやアプリのアップデートも忘れずに行いましょう。
パスワードを適切に管理する
パスワードの使い回しや単純な組み合わせ(例:123456)は非常に危険です。
8文字以上・英数記号を混ぜた強固なパスワードを使いましょう。
管理にはパスワード管理アプリの利用が便利です。定期的な変更も推奨されます。
情報保護を習慣化する
日常的に意識することで、情報漏洩リスクを大幅に軽減できます。
スマホやPCのロック設定、ログイン後の自動ログアウト、不要なアプリの削除など、毎日の行動にセキュリティ意識を組み込みましょう。
意識が最大の防御です。
企業が実践すべき情報漏洩対策

企業にとって、従業員や顧客の情報を守ることは、信頼維持と事業継続の土台となります。
以下のような対策を徹底しましょう。
教育と社内ルールを徹底する
情報漏洩を防ぐためには、まず社員一人ひとりの意識向上が欠かせません。
定期的なセキュリティ教育や研修を実施し、情報管理の重要性や具体的なルールを周知徹底しましょう。
また、違反時のペナルティや行動指針を明文化し、社内規定として明確に示すことが重要です。
誤送信や持ち出しを防止する
メールの誤送信や情報の持ち出しは、企業の情報漏洩リスクの大きな要因です。
送信前の内容確認や宛先の二重チェック、外部記憶媒体の利用制限などの対策を講じましょう。
また、ファイルの暗号化や社外への送信を制限するシステム導入も効果的です。
| 対策項目 | 内容例 | 効果 |
|---|---|---|
| 送信前確認のルール | 宛先・添付ファイルのダブルチェック | 誤送信の防止 |
| 外部記憶媒体制限 | USBや外付けHDDの利用制限 | 情報の不正持ち出し防止 |
| メールの暗号化 | 重要情報を暗号化して送信 | 第三者による情報取得の抑止 |
報告しやすい環境を整える
情報漏洩リスクの早期発見・対処には、社員が不安や問題を気軽に報告できる環境作りが必要です。
匿名での通報窓口設置や、報告者の保護ルールを整備しましょう。
報告を促進するために、定期的なフォローアップや啓発活動も効果的です。
守秘義務の認知を強化する
守秘義務は情報漏洩防止の根幹です。
全社員に対して守秘義務の法的意味と重要性を理解させる教育を実施し、契約書への署名や定期的な確認を行いましょう。
特に退職時の注意点や第三者への情報提供の禁止事項は強調が必要です。
管理体制を強化する
情報漏洩対策には、組織全体の管理体制の強化が不可欠です。
責任者の明確化や権限の適正配分、監査や評価制度の導入により、対策の実効性を確保します。
さらに、システムのアクセス権管理やログ管理を徹底し、問題発生時の追跡を可能にしましょう。
管理体制のチェックリスト
- 情報セキュリティ責任者を任命している
- 権限管理ルールを整備している
- 定期的な監査・評価を実施している
- アクセスログの取得と分析を行っている
まとめ|個人の情報を守るためにできること

個人情報の漏洩は、一度起これば信用を大きく損なうだけでなく、金銭的な被害にも発展します。
自分自身でできる対策を習慣化し、企業としても継続的な教育とルール整備が不可欠です。
自社に合った対策をプロと構築する
情報漏洩対策は、単にセキュリティソフトを導入すれば完了するものではありません。
企業ごとの業種や規模、ネットワーク構成に応じたオーダーメイドの対策が必要です。
専門知識を持つプロのサポートを受けながら、適切な体制を整えていきましょう。
法人向け相談はITDへ
ネットワークセキュリティに関するご相談は、ぜひITDにお任せください。
「ITD」は、通信機器・OA機器の販売から、工事・保守まで一貫して対応する企業です。
高性能なUTM機器のリース導入にも対応しており、初期費用を抑えながら堅牢なセキュリティ環境を構築できます。
「何から始めればいいかわからない」「現在のセキュリティに不安がある」といったお悩みをお持ちの方には、無料の現地訪問・見積もりサービスをご用意しています。
専門スタッフが丁寧にヒアリングし、最適なプランをご提案します。
オフィスの常識を変えるよう、株式会社ITDが貴社の業務改善とセキュリティ強化をサポートいたします。
ぜひ一度、お気軽にご相談ください。
↓👇下記お問い合わせより、お気軽にご連絡ください!即対応いたします!👇↓