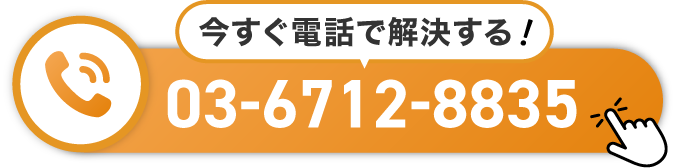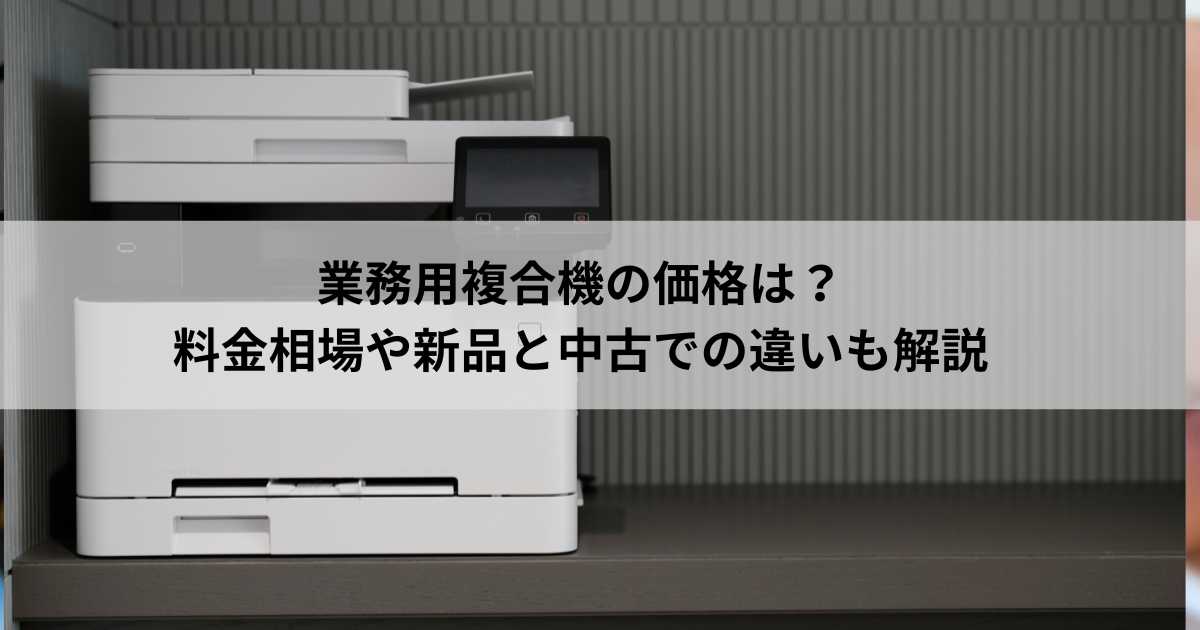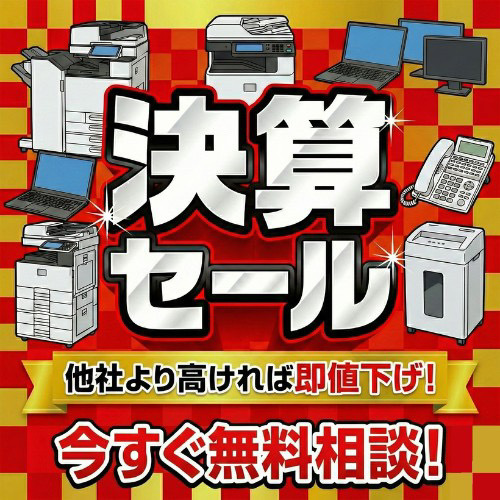複合機の耐用年数は?耐用年数や国税庁の資料から減価償却の計算方法
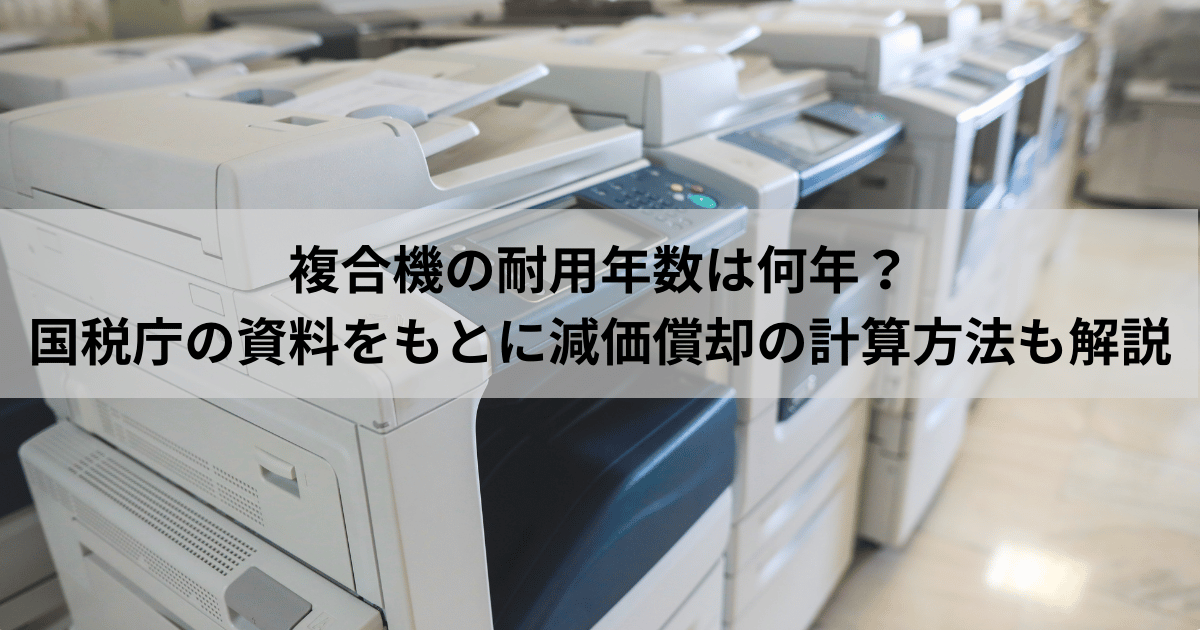
複合機は、企業のオフィスで日常的に使用される重要な設備です。
しかし、その耐用年数や減価償却の方法について、具体的に知っている人は少ないかもしれません。
本記事では、複合機の耐用年数や減価償却について、わかりやすく解説します。
- 複合機の長期的な運用を計画しているオフィス管理者やIT担当者
- 複合機の選定基準や設置環境、メンテナンスの重要性について再確認したいと考えている方
- 自社の複合機を長く使いたい、耐用年数を延ばすための適切なケア方法を知りたい方
複合機の耐用年数とは?

まず、複合機の耐用年数について理解しましょう。
耐用年数とは、税法上、資産が使用できる期間を示すもので、減価償却を計算する際の基準となります。
しかし、これはあくまで税務上の基準であり、実際の使用期間を制限するものではありません。
法定耐用年数とは
法定耐用年数とは、税務上、資産の価値が減少する期間として定められた年数です。
これは、国税庁によって設定されており、資産の種類ごとに異なります。
複合機の場合、一般的には法定耐用年数が「5年」とされています。
使用期間を制限するものではない
法定耐用年数はあくまで税務上の基準であり、実際の使用期間を制限するものではありません。
たとえば、法定耐用年数が5年であっても、適切なメンテナンスや修理を行えば、それ以上使用することが可能です。
法定耐用年数を越えて使用することも、違法ではありません。
耐用年数=買い替え時期ではない
また、耐用年数が来たからといって、必ずしも買い替えが必要なわけではありません。
複合機が問題なく動作している場合は、そのまま使用を継続しても問題ありません。
しかし、老朽化や性能の低下が見られる場合は、新しい複合機への買い替えを検討することが望ましいです。
複合機は10年以上使うケースもある
複合機の買い替え時期は、本当にさまざまです。
実際には5年を超えて使用されているケースも多くあります。
あくまで、法定上の耐用年数のため、使える場合は長く使いましょう。
多くの事業者では、10年以上使うケースも多いようです。
稀に、印刷枚数が非常に多い場合は、5年未満で寿命を迎える可能性もあるそうですが、複合機のテクノロジーも進化しており、あまりそのようなケースは少ないと言えるでしょう。
複合機の耐用「枚数」はある?
複合機の「耐用年数」についてはよく耳にしますが、実際には「耐用枚数」という概念も存在します。
多くのメーカーは、複合機の「耐用枚数」を目安として公開しており、これは設計寿命に基づいています。
100万枚から300万枚程度であることが一般的です。
基本は、メーカーや機種によって異なり、使用目的や印刷頻度によっても影響を受けます。
小規模オフィスであっても、100万枚から300万枚程度の機種をおすすめします。
複合機の減価償却の計算方法

次に、複合機の減価償却の方法について見ていきましょう。
減価償却とは、資産の価値が時間の経過とともに減少することを会計上で表す手法です。
複合機などの固定資産は、購入した年に一括して費用計上するのではなく、法定耐用年数にわたって少しずつ費用を分割して計上します。
減価償却とは
減価償却は、購入した資産の価値を経年に応じて費用として計上する会計処理です。
これにより、資産がもたらす経済的利益を正確に反映し、企業の財務状況を適切に評価することができます。
定額法
定額法は、毎年同じ額を減価償却費として計上する方法です。
複合機の耐用年数が5年であれば、購入金額を5で割り、その額を毎年の費用として計上します。
この方法はシンプルで、年間の費用が一定であるため、財務管理が容易です。
計算方法
「取得金額×償却率」
計算方法例
耐用年数が5年なので、定額法償却率は、1 ÷ 5 = 0.20 です。
1年目から5年目まで、毎年均等に減価償却を行います。
- 1年目:100万円 × 0.20 = 20万円
- 2年目:100万円 × 0.20 = 20万円
- 3年目:100万円 × 0.20 = 20万円
- 4年目:100万円 × 0.20 = 20万円
- 5年目:19万9,999円(利用中の資産であることを示すために、全額償却せずに1円を残す)
定率法
定率法は、資産の残存価額に一定の率を掛けて減価償却費を計算する方法です。
初年度に多くの費用を計上し、徐々に減らしていくという特性があります。
複合機のような資産価値が早期に減少する可能性がある場合、定率法が適用されることが多いです。
計算方法
「減価償却費=未償却残高×定率法の償却率」
計算方法例
耐用年数が5年の場合、定率法の償却率は、1 ÷ 5 × 2 = 0.40(定率法の償却率は通常、定額法償却率の2倍)です。
減価償却費の計算: 定率法では、残存価額に0.40を掛けて計算します。
- 1年目:100万円 × 0.40 = 40万円
- 2年目:(100万円 – 40万円)× 0.40 = 24万円
- 3年目:(60万円 – 24万円)× 0.40 = 14.4万円
- 4年目:(36万円 – 14.4万円)× 0.40 = 8.64万円
- 5年目:8.63万円(利用中の資産であることを示すために、全額償却せずに1円を残す)
このように、定額法は毎年同じ額が計上されるのに対し、定率法は年々減価償却額が減少していきます。
複合機の耐用年数を10年以上伸ばすコツ5選
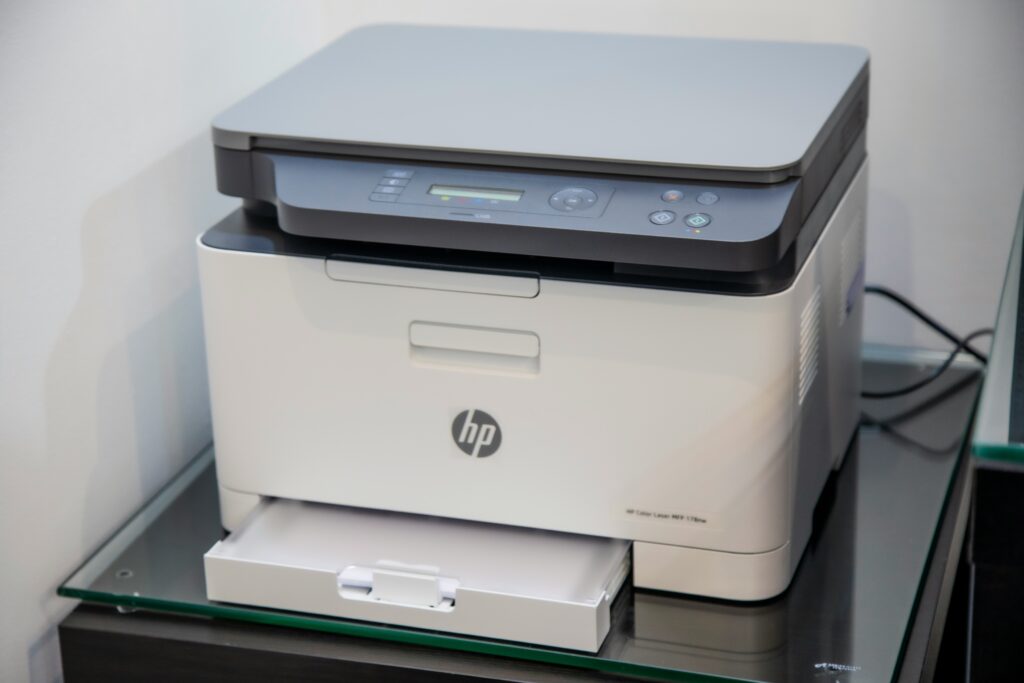
定期的にメンテナンスを行う
複合機の耐用年数を延ばすためには、定期的なメンテナンスが不可欠です。
印刷ヘッドやローラー部分などの清掃や部品の確認を行い、故障のリスクを減らすことで、長期間安定して使用することができます。
専門業者による点検もおすすめです。
設置環境に配慮する
複合機を設置する場所の環境が耐用年数に大きく影響します。
湿気や直射日光を避け、風通しの良い場所を選ぶことが重要です。
過度な温度変化や湿気が機器内部に影響を及ぼし、故障の原因となる可能性があります。
正しい方法で印刷する
複合機を長持ちさせるためには、正しい印刷方法を守ることが大切です。
過剰な枚数や高解像度での連続印刷を避け、必要な設定を行うことで、機器にかかる負担を減らし、耐用年数を延ばすことができます。
主電源は落とさないようにする
複合機の電源を頻繁にオンオフすることは、機器にストレスを与える原因となります。
長期間使用しない場合でも、主電源を落とさず、スタンバイモードでの使用を推奨します。これにより機器の寿命が延びます。
定期的に印刷する
複合機を長持ちさせるためには、定期的に印刷を行うことが重要です。
長期間使用しないと、インクが固まったり、部品が動かなくなったりすることがあります。
月に1度でも印刷を行うことで、機器の動作を保ち、トラブルを防ぐことができます。
複合機の減価償却における注意点するべき3つのポイント

減価償却を行う際にはいくつかの注意点があります。特に法人の場合は、以下の点に注意が必要です。
耐用年数を正確に設定する重要性を理解する
法人が減価償却を行う場合、原則として定率法が適用されます。
これは税法による規定であり、企業が資産を購入する際に、初期費用を大きく計上することで早期に経費として落とすことができるためです。
ただし、特定の条件下では定額法を選択することも可能です。これは税理士と相談しましょう。
購入価格に応じた適切な勘定科目を選択する
複合機の購入価格に応じて、適切な勘定科目を選択することが重要です。
購入金額が一定額以上の場合、固定資産として扱い、減価償却の対象になります。
小額であれば消耗品費として処理できる場合もあります。
税務署の基準を確認し、勘定科目を誤らないようにしましょう。
また、勘定科目の選定ミスは税務上のリスクを引き起こす可能性があるため、慎重に決定することが求められます。
償却資産を処分する際の手続き方法を確認する
複合機を処分する際には、適切な手続きが必要です。
償却資産を売却または廃棄する場合、その資産の帳簿価額と処分額との差額を計算し、税務申告を行う必要があります。
処分時に発生した利益や損失は、確定申告で申告する義務が生じます。
処分手続きに不備があると、税務署から指摘を受けることがあるため、事前に正しい手順を把握し、適切に処理を行いましょう。
自社に最適な複合機を選ぶのは難しい?

複合機の選定は、企業の業務効率やコストに大きく影響するため、慎重に考えるべき重要な決断です。
しかし、選択肢が多いため、どれが最適なのか迷うことも多いでしょう。
「複合機は、購入かリースか長期的に見てどちらがお得なのか?」
「複合機の減価償却は定額法で行いたいが、自社のケースだと定率法にしたほうが良いのか?」
複合機を選ぶ際には、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。
以下に、自社に最適な複合機を選ぶための要点をまとめました。
- 自社のニーズや必要なスペックを明確にする
- 買い替えかリースかを検討する
- 複合機の耐用年数を考慮する
- メンテナンスとサポート体制を確認する
- 長期的なコストを比較する
- 機能と使いやすさを重視する
しかし、上記以外にも長く利用する上では注意しないとならないポイントが数多くあります。
業界歴10年を越えるベテランスタッフが在籍するITDではそのような相談を一括でお引き受けしております。
複合機もかなりお安い導入費用からご提案可能なので、お気軽にお問い合わせください。
↓👇下記お問い合わせより、お気軽にご連絡ください!即対応いたします!👇↓