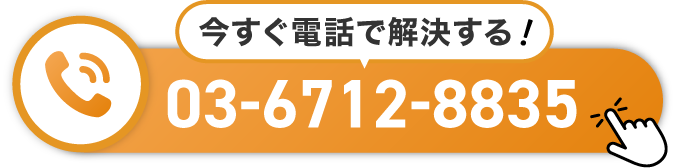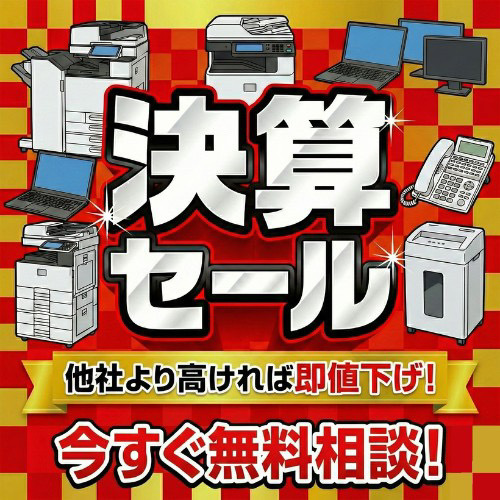クリックフィックス被害とは?サイバー攻撃の実態と企業ができる対策も
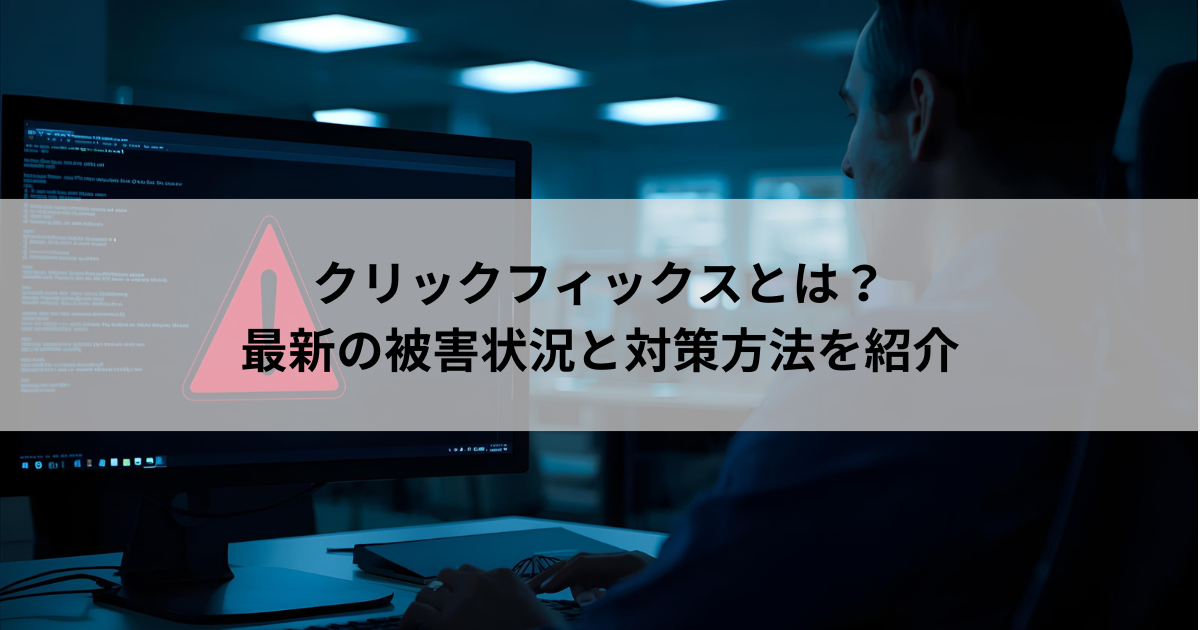
企業のパソコン画面に突然「ウイルス感染しました」といった警告が表示されるクリックフィックス被害。
誤ってクリックしてしまうと、情報漏えいやウイルス感染につながる恐れがあります。
本記事では、企業が行うべきクリックフィックス対策や、被害を防ぐための具体策を紹介します。
- クリックフィックス被害について知りたい人
- クリックフィックスの被害にあってしまった人
- セキュリティ対策を見直したい人
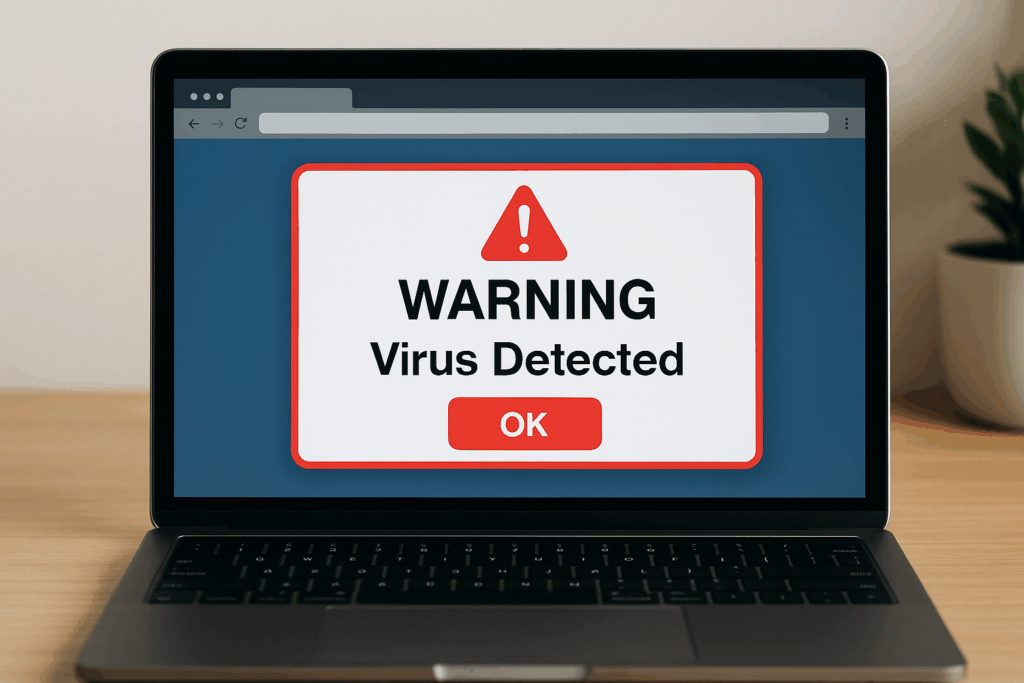
クリックフィックスの特徴とは?
偽のセキュリティ警告やポップアップが表示される
「クリックフィックス(ClickFix)」とは、偽の警告画面やポップアップを表示してユーザーをだまし、不正サイトへ誘導するサイバー詐欺の一種です。
見た目はセキュリティ警告やシステム通知のように装われており、うっかりクリックしてしまうことでマルウェア感染や個人情報の流出につながるケースがあります。
特に最近では、クリックフィックス被害がスマートフォンやパソコンのどちらでも報告されており、誰でも被害に遭う可能性があります。
「ロボットではありません」などのボタンをクリックさせる
最も多いパターンは、「ウイルスに感染しています」「今すぐ修復してください」といった偽のセキュリティ警告が表示されるケースです。
ユーザーの不安をあおり、「修復」や「OK」と書かれたボタンをクリックさせようとします。
中には、「ロボットではありません」など一見安全そうな確認ボタンを使って安心感を与える巧妙な手口もあります。
また、キーボードを操作させる被害も多発しています。
有害サイトへ飛ばされる
ボタンをクリックすると、別の有害サイトやダウンロードページへ飛ばされ、不要なアプリや偽のウイルス対策ソフトをインストールさせられることがあります。
これらのソフトは実際にはウイルス駆除を行わず、代わりに不正なプログラムを仕込んだり、個人情報を抜き取ったりする危険なものです。
また、警告メッセージを閉じようとしても何度も表示が繰り返され、ユーザーが正常に操作できなくなることもあります。
ブラウザ上で発生するケースが多い
クリックフィックスはブラウザ上で発生するケースが多いのも特徴です。
特定のサイトにアクセスしただけでポップアップが表示されることがあり、メールやSNS、検索結果の広告経由で誘導されることもあります。
一見セキュリティ関連の正規サイトに見える
見た目がGoogleやMicrosoftなどの正規セキュリティページに似せて作られているため、IT知識がある人でも一瞬だまされてしまうほどです。
個人情報の入力を促されることもある
さらに厄介なのは、クリック後に個人情報の入力を求められるケースです。
「ライセンス登録のため」「サポートのために必要です」などと表示され、氏名・メールアドレス・クレジットカード情報などを入力させようとします。
こうした情報が悪用されると、不正請求やアカウント乗っ取りといった二次被害につながる恐れがあります。
クリックフィックスのリスク
クリックフィックス被害は単なる迷惑広告ではなく、金銭・情報・企業信用のすべてに関わる深刻なサイバーリスクです。
不正なプログラムやマルウェアのインストール
クリックフィックス被害の最大のリスクは、不正なプログラムやマルウェアをインストールしてしまうことです。
偽の警告画面で「修復する」「ウイルスを削除」といったボタンをクリックすると、実際にはウイルスを駆除するどころか、新たなマルウェアをダウンロードしてしまうケースがあります。
このマルウェアは、PCの動作を遅くしたり、システム設定を勝手に変更したり、さらには外部の攻撃者と通信して情報を抜き取ったりと、深刻な被害を引き起こします。
自覚のないまま感染が広がる点も非常に危険です。
個人情報の流出
クリックフィックスは、ユーザーの不安を利用して個人情報を入力させる手口を取る場合があります。
たとえば、「セキュリティライセンスの更新」「購入手続きの確認」などの名目で、氏名・メールアドレス・電話番号・クレジットカード番号などを入力させるケースです。
こうして入力された情報は、攻撃者のサーバーに送られ、悪用されるおそれがあります。
結果として、クレジットカードの不正利用やアカウント乗っ取りといった二次被害に発展することも少なくありません。
社内ネットワーク全体へのウイルス拡散
特に注意すべきなのが、企業や組織で使用しているPCが感染した場合です。
1台の端末から社内ネットワーク全体にウイルスが拡散し、共有サーバーや他の端末にも被害が及ぶ可能性があります。
ネットワークに侵入された場合、業務データの改ざんや漏えい、取引先への攻撃など、連鎖的な被害が発生するリスクもあります。
情報セキュリティ体制が不十分な中小企業では、たった1回のクリックが企業の信用を失うきっかけになることもあるため、早期の対策が欠かせません。
有料ソフトの購入・課金
クリックフィックス被害の中には、「ウイルスを駆除するにはこのソフトが必要です」といった表示で有料ソフトの購入を迫るケースもあります。
これらのソフトは正規品ではなく、支払いをしても機能しない、あるいはさらに危険なプログラムを仕込まれる可能性があります。
また、クレジットカード情報を入力することで金銭的被害だけでなく、前述のような情報漏えいにもつながります。
「今すぐ対処しなければ危険」と焦らせる表示が出ても、冷静に確認することが重要です。
クリックフィックスにあってしまったら
クリックフィックスの被害は、一瞬のクリックから始まります。
しかし、もし被害に遭ってしまっても、冷静に正しい対応を取ることで被害を最小限に抑えることが可能です。
慌ててボタンを押したり、表示された連絡先に電話をかけたりすると被害が拡大する恐れがあるため、まずは落ち着いて以下の手順を実行しましょう。
すぐにブラウザやアプリを閉じる
偽の警告やポップアップが表示されたら、まずはその画面をすぐに閉じることが最優先です。
焦って「閉じる」ボタンや「OK」ボタンを押すと、さらに別の有害サイトへ飛ばされる場合があります。
安全に閉じるには、ブラウザやアプリ自体を強制終了させる方法がおすすめです。
Windowsなら「Ctrl+Alt+Delete」、Macなら「Command+Option+Esc」で強制終了画面を開けます。
スマートフォンの場合は、マルチタスク画面から該当アプリをスワイプして終了しましょう。
不正なアプリや拡張機能が入っていないか確認する
クリックフィックス被害の多くは、クリック後に不正なアプリやブラウザ拡張機能が自動的に追加されます。
設定画面やアプリ一覧を開き、見覚えのないソフトが入っていないかを確認してください。
特に「Security」「Cleaner」「Fix」など、セキュリティを装った名前のアプリには注意が必要です。
不要なプログラムが見つかった場合はすぐにアンインストールし、セキュリティソフトでフルスキャンを行いましょう。
パスワードを入力してしまった場合は変更する
もしクリック後の画面でパスワードやクレジットカード情報を入力してしまった場合は、すぐに対処することが重要です。
ログイン情報を入力したサイトと同じパスワードを他でも使っている場合は、すべてのサービスで変更してください。
クレジットカード情報を入力してしまった場合は、カード会社に連絡し、不正利用の確認や利用停止の手続きを依頼します。
被害を早期に発見できれば、金銭的被害を防げる可能性が高まります。
情報システム部門や専門業者に相談する
企業の端末でクリックフィックスに遭った場合は、自己判断で操作せず、必ず情報システム部門に報告してください。
ネットワーク全体に感染が広がっている可能性があるため、被害範囲の確認や通信遮断などの初動対応が必要です。
個人で対応できない場合や感染の疑いが強い場合は、セキュリティ専門業者に診断・駆除を依頼するのが安全です。
場合によっては、警察のサイバー犯罪相談窓口や消費生活センターへの相談も有効です。
企業がクリックフィックスを防ぐ方法
クリックフィックス被害は、個人だけでなく企業にとっても深刻な脅威です。
近年は、攻撃者が企業のセキュリティのすき間を狙う手口が増加しており、組織的な対策が欠かせません。
ここでは、企業がクリックフィックス被害を未然に防ぐために実施すべき主なポイントを紹介します。
不審なリンクをクリックしない
最も基本的で、かつ効果的な防止策は、社員一人ひとりが不審なリンクをクリックしないことです。
攻撃者は、「ウイルス検出」「アカウント停止」「請求確認」など、もっともらしい文言で警告を装います。
メールやチャット、SNSなど、社内外を問わず不審なURLを開かないという意識を全員が持つことが大切です。
定期的に情報セキュリティ研修を実施し、「不自然な日本語」「差出人アドレス」「リンク先のドメイン」など、詐欺サイトを見分ける目を養うことが重要です。
OSは常に最新版へアップデートしておく
古いバージョンのOSやソフトウェアには、脆弱性(セキュリティ上の弱点)が残っていることがあります。
攻撃者はこの脆弱性を悪用して、不正プログラムを送り込んだり、ブラウザ上で偽ポップアップを表示させたりします。
クリックフィックスのような攻撃を防ぐには、常に最新の状態を保つことが鉄則です。
Windows UpdateやmacOSのソフトウェア更新を自動化し、社員が勝手に更新を止めないよう社内ルールを定めておくと効果的です。
UTMやWebフィルタリングなどの多層防御システムを導入する
さらに効果的なのが、UTM(統合脅威管理)やWebフィルタリングなどの多層防御システムの導入です。
これらの機器は、外部からの不正通信や危険サイトへのアクセスをネットワークレベルで遮断し、社員が誤ってクリックしても被害を最小限に抑えられます。
UTMを導入すれば、ウイルス対策・不正侵入防止・スパムメール対策を一括で行えるため、コストパフォーマンスにも優れています。
近年では、中小企業向けに手軽に導入できるモデルも増えており、「人の注意」と「システム防御」を組み合わせることが最も効果的な対策といえます。
オフィスのセキュリティ対策ならITD

どこよりもコスパよく、企業の安心を支えます。
ITDでは、UTMやビジネスフォン、ネットワーク構築など、中小企業でも導入しやすい価格でトータルセキュリティを提供しています。
クリックフィックス対策をはじめ、迷惑メール・不正アクセス・ウイルス感染など、あらゆるリスクをワンストップで防御可能です。
「初期費用を抑えたい」「リースで導入したい」「何から始めればいいかわからない」そんな企業様も、ぜひ一度ITDへご相談ください。
↓👇お客様の環境・ご予算に合わせて、最適なセキュリティ対策をどこよりもコスパよくご提案します!👇↓
※お問い合わせの際は、「キャッシュバックバナーを見た」とお伝えください。