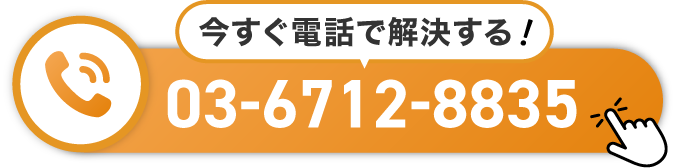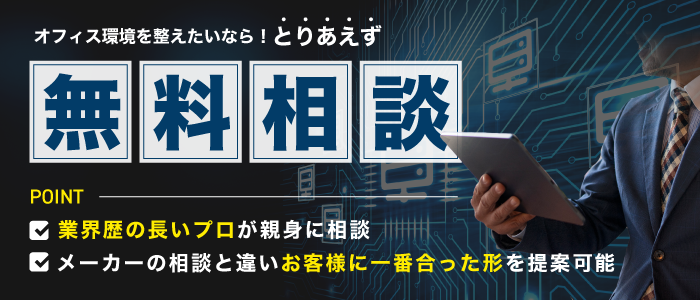会社のアドレスに迷惑メールが多いときはどうする?企業ができる対策も
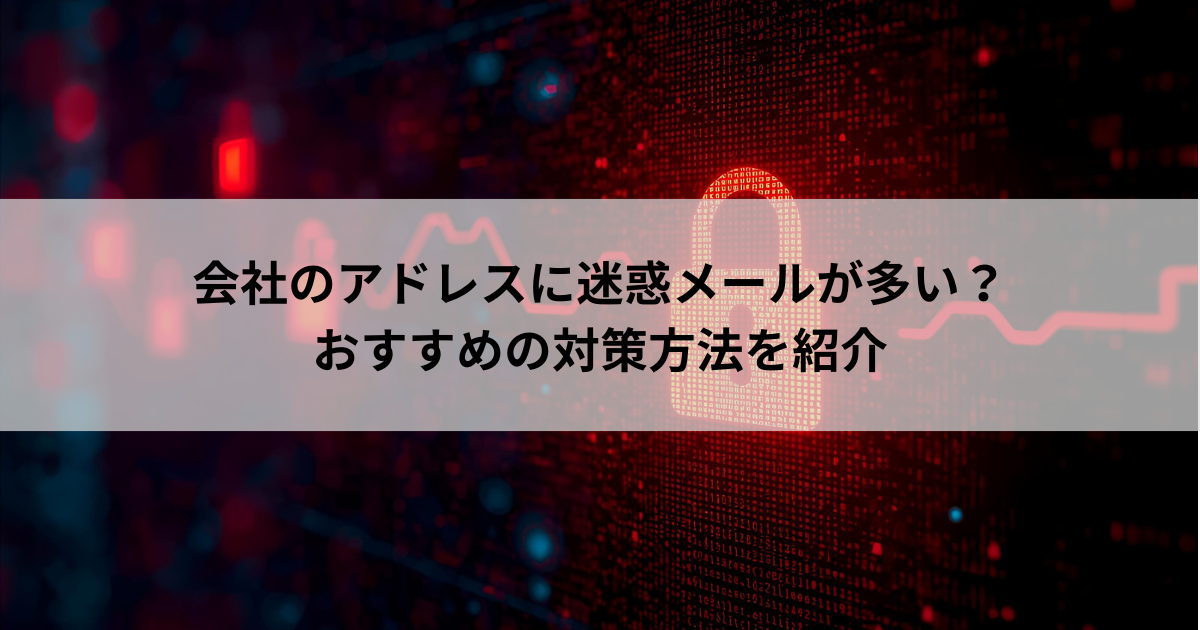
企業のメールアドレスには、日々多くの迷惑メールが届いています。
中にはマルウェア感染や情報漏えいにつながる危険なものもあり、放置すれば大きな損害を招くおそれがあります。
特に中小企業では、人手やコストの制約から十分な対策が取れていないケースもあります。
この記事では、迷惑メールの原因やリスク、効果的な対策方法をわかりやすく解説します。
- 迷惑メールが多く困っている人
- スパムメールの対策をしたい人
- 情報漏えいのリスクを軽減したい人

企業への迷惑メールが多い原因
情報が資産として取引されている
企業のメールアドレスは、今や「データ資産」として価値を持っています。
営業リストやマーケティング資料として売買されるケースも多く、特にWebサイトで公開されている「info@」「contact@」などのアドレスは、自動収集プログラム(スクレイピング)によって簡単にリスト化されます。
こうして集められた情報は、正規のマーケティングだけでなく、迷惑メールの送信リストとしても悪用されてしまうのです。
迷惑メール送信者のビジネスモデルが存在する
迷惑メールの多くは、単なる嫌がらせではなく、明確な収益構造のもとで行われています。
開封率がごくわずかでも、数百万件単位で送信すれば広告収入や詐欺による利益が得られるため、送信コストの安さも相まって止まることがありません。
特に「社名入り」や「業界特化型」のメールは、企業担当者が開きやすいよう工夫されており、巧妙化が進んでいます。
サプライチェーン全体で情報が拡散している
近年では、自社だけでなく取引先や外注先など、サプライチェーン全体で情報が共有されるケースが一般的になりました。
その中で、どこか一社の管理体制が甘いと、メールアドレス情報が漏えいし、結果的に迷惑メールの対象となってしまいます。
中小企業ほど情報セキュリティ対策に差が出やすく、知らないうちに自社の連絡先が流出していることもあります。
迷惑メールを受け取ることのリスク
マルウェア感染リスク
迷惑メールには、添付ファイルや本文中のURLリンクにウイルスやランサムウェアが仕込まれていることがあります。
特に、請求書・配送通知・取引確認といった業務メールを装ったスパムは巧妙で、社員がうっかり開いてしまうケースも少なくありません。
感染すると、社内サーバーや共有フォルダまで被害が拡大し、業務データが暗号化される、復旧に多大なコストがかかるなど、深刻な損害を招くおそれがあります。
メールを開くだけで感染するタイプもあり、一通の迷惑メールが全社的なトラブルの引き金となりかねません。
フィッシング詐欺による情報漏えい
もう一つの大きなリスクが、フィッシングメールによる情報漏えいです。
銀行や取引先企業、クラウドサービスなどを装って「パスワード再設定」や「本人確認」を促し、偽サイトへ誘導する手口が増えています。
企業の業務メールは日々大量に届くため、社員が本物と偽物を見分けられず、誤ってログイン情報を入力してしまうこともあります。
こうして盗み取られた認証情報は、社内システムへの不正侵入や顧客情報の流出につながり、企業の信頼を一瞬で失う事態にもなりかねません。
情報漏えい・法的リスク
迷惑メールをきっかけとしたマルウェア感染やフィッシング被害により、顧客情報・取引情報の漏えいが発生すると、企業は大きな法的責任を負う可能性があります。
個人情報保護法の改正以降、企業の管理体制が不十分だった場合、行政処分や損害賠償請求を受けることも珍しくありません。
また、一度漏えい事故を起こすと、取引停止や信用失墜などの二次被害にも発展します。
こうしたリスクを回避するには、迷惑メールを「ただのスパム」と軽視せず、企業のセキュリティリスクの入口として位置づけ、日常的に防御体制を整えることが重要です。
企業ができる迷惑メール対策
メールサーバーでのフィルタリング強化
企業がまず行うべき基本対策は、メールサーバーのフィルタリング強化です。
サーバー側でスパム判定を行い、疑わしいメールを自動的に迷惑メールフォルダへ振り分けることで、社員が誤って開封するリスクを大幅に減らせます。
ブラックリスト・ホワイトリストを設定し、信頼できる送信元だけを受信できるようにすることも有効です。
また、サーバー管理者が定期的に設定を見直し、スパム検知率を高めることが重要です。
クラウドメールサービスを利用している場合も、管理画面から迷惑メールフィルタを強化しておきましょう。
ドメイン認証の導入
送信ドメイン認証の設定は、なりすましメール対策の基本です。
SPFは送信元サーバーの正当性を確認し、DKIMはメール本文の改ざんを検知します。
さらにDMARCを組み合わせることで、受信側サーバーが不正メールを自動的に拒否するようになります。
これらを設定することで、自社のドメインがスパム発信源と誤認されるリスクも低下します。
特に取引先と頻繁にメールをやり取りする企業では、ドメイン認証の有無が信頼性の判断材料となるため、早期導入が推奨されます。
Outlook・パソコンでの受信拒否設定
個々の社員が利用するメールソフト側でも、受信拒否設定の強化が欠かせません。
Outlookの場合、「迷惑メールオプション」を活用すれば、スパムメールを自動で振り分けたり、特定の差出人やドメインをブロックしたりできます。
さらに、迷惑メールとしてマークした送信元情報は学習され、次回以降は自動で検知されるようになります。
社員一人ひとりが設定を見直すことで、組織全体のリスクを減らすことにつながります。
セキュリティソフト・ウイルス対策の常時更新
ウイルスやマルウェアの手口は日々進化しています。
セキュリティソフトを常に最新の状態に保つことが、迷惑メール対策の基本です。
定義ファイルを自動更新に設定し、新種のスパムメールや不正リンクにも対応できるようにしておきましょう。
万が一感染しても、早期検知・隔離が可能になります。
組織全体での多層防御
メールだけでなく、ネットワーク全体での多層防御も欠かせません。
UTM(統合脅威管理)を導入すれば、スパム・ウイルス・不正アクセスなど複数の脅威をまとめて防御できます。
社員教育やアクセス制御といった運用面の対策も組み合わせることで、より強固なセキュリティ体制が構築できます。
迷惑メール対策は個人任せにせず、会社全体で「受け取らない・開かせない・広げない」環境を整えることが何より重要です。
迷惑メールを開いてしまったときの対処法
添付ファイルやリンクを開かない
迷惑メールを誤って開いてしまっても、添付ファイルや本文中のリンクには絶対に触れないことが大切です。
請求書や支払い確認を装ったメールにPDFやZIPファイルが添付されている場合、それを開くとウイルス感染や不正通信が発生する恐れがあります。
また、「詳細はこちら」などのリンクから偽サイトに誘導されるケースもあります。
少しでも不審に感じたら、内容を確認せずにすぐ削除しましょう。
感染の可能性がある場合はネットワークを遮断する
万が一、添付ファイルを開いたり、リンクをクリックしてしまった場合は、まずネットワークを遮断してください。
LANケーブルを抜く、Wi-Fiをオフにするなどして、感染拡大を防止します。
ウイルスは社内ネットワーク経由で他の端末やサーバーに拡散することがあるため、初動対応が重要です。
電源を落とすよりも先に通信を切断することで、被害の拡大を最小限に抑えられます。
管理者・情報システム部門へ報告する
次に、管理者や情報システム部門に速やかに報告します。
いつ、どのメールを開いたのか、どのような操作をしたのかを正確に伝えることで、被害範囲の特定や感染経路の調査がスムーズになります。
自己判断で削除してしまうと証拠が残らず、対応が遅れる原因になります。
報告体制をあらかじめ社内で整備しておくことも、企業としての重要な備えです。
セキュリティスキャン・ログ確認
報告後は、セキュリティソフトでのフルスキャンを実行し、感染の有無を確認します。
UTMやメールサーバーのログも確認し、外部通信や不正アクセスの痕跡がないかをチェックします。
問題が見つからなかった場合でも安心せず、今後同じミスを防ぐために、社員全体で注意喚起を行いましょう。
迷惑メールを開いてしまった経験を「社内共有の学び」として活かすことが、再発防止につながります。
迷惑メール対策にはUTMが最適な理由
迷惑メールを入口でブロックできる
UTM(統合脅威管理)は、外部からの不正アクセスや迷惑メールを「入口」で遮断できるのが最大の強みです。
サーバーやPCに届く前にフィルタリングを行うため、従業員が誤って開封してしまうリスクを大幅に減らせます。
特に中小企業では、IT担当者が少なく個々のPC設定に依存しがちですが、UTMを導入することで組織全体のメールセキュリティを一括管理できます。
マルウェア・URLフィルタで多層防御できる
迷惑メールには、悪意ある添付ファイルや偽サイトへのリンクが仕込まれているケースも多く見られます。
UTMはウイルスチェック機能やURLフィルタリング機能を備えており、危険な通信を自動的に遮断します。
単なるメールフィルタでは防ぎきれない巧妙な攻撃にも対応できるため、「万が一」への備えとしても効果的です。
他のセキュリティ機能も同時に実装できる
UTMは、メール対策だけでなく、ファイアウォール・不正侵入検知・Webフィルタリングなど、複数のセキュリティ機能を統合的に運用できます。
これにより、ネットワーク全体の安全性をワンストップで確保でき、コスト面でも非常に効率的です。
セキュリティ対策を後回しにしがちな中小企業こそ、限られたリソースで最大限の防御を実現できるUTMの導入が有効です。
日々増え続けるサイバー攻撃から会社を守るためにも、「メール対策=UTM」で早めの一歩を踏み出しましょう。
迷惑メール対策ならITD

迷惑メール対策は、いまや企業の規模を問わず必須のセキュリティ対策です。
UTMの導入により、メールをはじめとしたサイバー攻撃の脅威を“入口”で遮断し、組織全体を守ることができます。
ITDでは、どこよりもコスパよく、中小企業でも導入しやすい価格設定と、導入後のサポート体制で安心のセキュリティ環境を実現します。
↓👇「コストを抑えつつ確実に守りたい」そんな企業こそ、ぜひITDにご相談ください!👇↓
※お問い合わせの際は、「無料相談バナーを見た」とお伝えください。